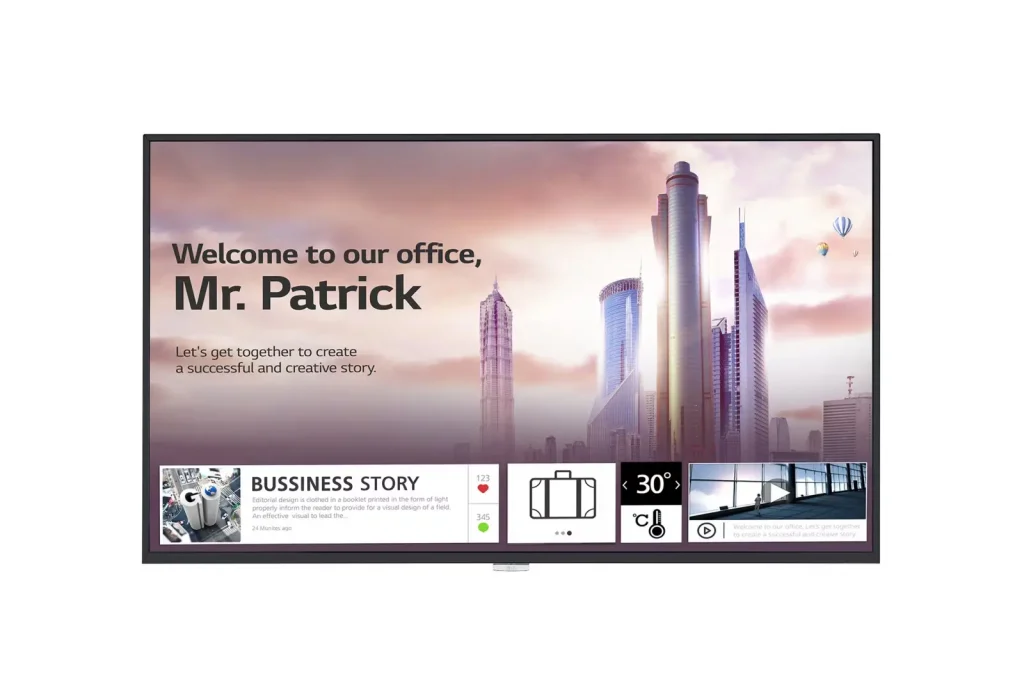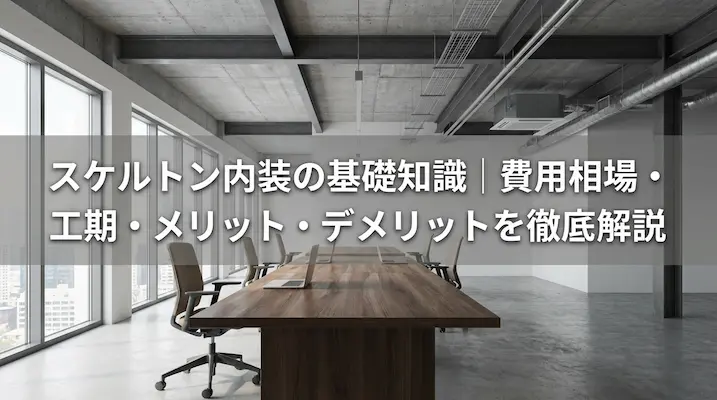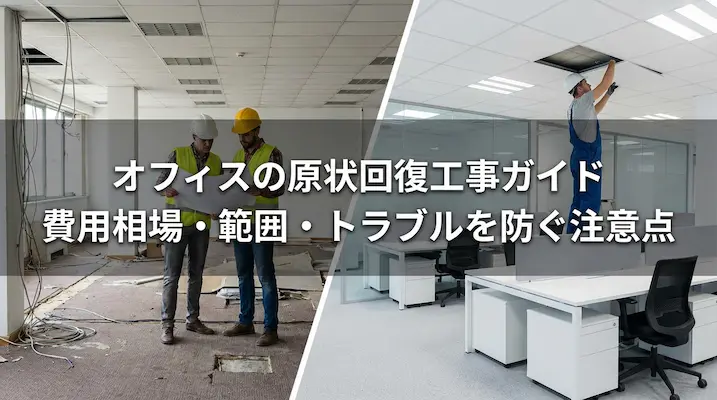デジタルサイネージの基本から選び方まで!用途別でわかる導入ガイド
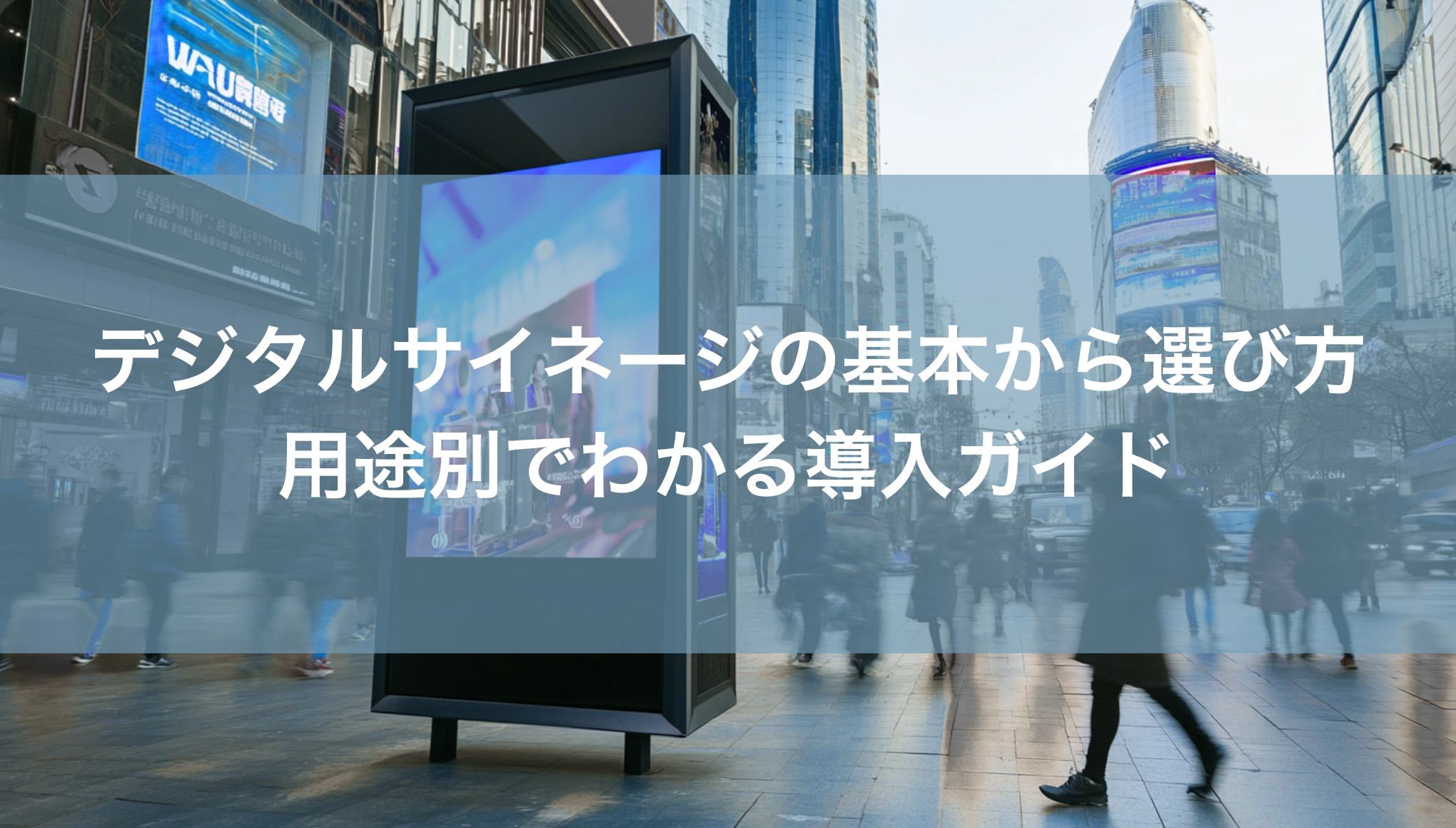
近年デジタルサイネージの導入が進み、オフィスや商業施設での情報発信の手段として注目されています。特にオフィスの移転やリニューアルの際に最新のデジタルサイネージを導入することで、社内コミュニケーションの活性化や業務効率の向上が期待できます。しかしデジタルサイネージにはさまざまな種類が存在するため、どの種類を選べばよいのか、どのように運用すれば効果的なのか、迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事ではデジタルサイネージの基本から、用途別の選び方、導入メリット、さらにはおすすめの製品まで詳しく解説します。オフィス環境に最適なデジタルサイネージを選ぶためのポイントを押さえ、スムーズな導入につなげましょう。
1.デジタルサイネージってどんなもの?
デジタルサイネージは、電子ディスプレイを活用した情報表示システムです。近年オフィスや商業施設、公共空間などでの導入が進み、紙のポスターや掲示板に代わる新しい情報発信ツールとして注目されています。デジタルコンテンツを活用することで視認性が高まり、かつリアルタイムで情報を更新できるため、柔軟な運用が可能です。
ここではデジタルサイネージの基本的な仕組みや特徴、そしてどのような場所で活用されているのかについて詳しく解説します。
デジタルサイネージの基本
デジタルサイネージとは、電子ディスプレイを使って広告や情報を発信するシステムのことです。従来の紙媒体と異なり、動画やアニメーションを活用できるため視認性が高く、リアルタイムで情報を更新できる点が大きな特徴です。また遠隔管理が可能なため、人件費削減や運用コストの最適化というメリットもあります。
デジタルサイネージのシステムは、主にディスプレイ、コンテンツ管理システム(CMS)、配信ネットワークの3つの要素で構成されます。
ディスプレイ
デジタルサイネージのディスプレイは、液晶(LCD)、有機EL(OLED)、LEDパネルなどがあり、設置環境に応じて適切なモデルを選ぶことが重要です。
屋内用はデザイン性や解像度を重視し、屋外用は高輝度や防水・防塵性能を備えた耐久性の高いものが求められます。またタッチパネル対応のモデルを選ぶことでインタラクティブな操作が可能になり、より効果的な情報発信が実現します。
コンテンツ管理システム(CMS)
デジタルサイネージのコンテンツを管理・更新するためのシステムがコンテンツ管理システム(CMS)です。
USBメモリを使って手動で更新するスタンドアロン型と、インターネットを利用して遠隔管理できるクラウド型の2種類があります。クラウド型を導入すれば複数拠点のデジタルサイネージを一括管理できるため、運用の効率化につながります。スケジュール配信機能を活用すれば、時間帯や曜日ごとに異なるコンテンツを自動更新することも可能です。
配信ネットワーク
デジタルサイネージのコンテンツ配信には、ローカルネットワーク型とインターネット型の2つの方式があります。
ローカルネットワーク型は社内LANを活用し、オフライン環境で安全に運用できるのが特徴です。一方インターネット型はクラウド型CMSと連携し、遠隔地からリアルタイムでコンテンツの更新が可能です。最近では5Gの活用によって大容量の動画コンテンツ配信やAIを活用したターゲティング広告の実施も容易になり、さらに高度な運用が可能になっています。
どんな場所で活用されているのか
デジタルサイネージはオフィスや商業施設をはじめ、公共施設や交通機関など、多様なシーンで情報発信の効率化に貢献しています。それぞれの活用場所に応じた役割やメリットを理解することで、より効果的な導入が可能になります。
オフィス環境での活用
デジタルサイネージを社内コミュニケーションツールとして活用するオフィスが増えています。
エントランスに設置すれば、来訪者向けに企業紹介やイベント情報を発信でき、ブランドイメージの向上につながります。また社内向けには、各フロアの会議室予約状況や社内ニュースをリアルタイムで表示し、業務の効率化を図ることが可能です。さらに社員向けの教育コンテンツを流すことで、研修の一環としても活用できます。
商業施設や店舗での活用
商業施設や店舗では、デジタルサイネージは販促ツールとして大きな役割を果たします。
例えば店頭に設置すれば、商品のプロモーション動画を流して集客を強化できます。レジ付近では特売情報や新商品の紹介を表示することで、追加購入を促す効果が期待できます。またAIを活用したターゲティング広告を導入すれば、来店者の年齢や性別に応じたコンテンツを自動で表示することも可能です。

公共施設や交通機関での活用
駅や空港、バスターミナルなどの交通機関では、デジタルサイネージが案内表示システムとして活躍しています。
運行情報や遅延情報をリアルタイムで配信することで、利用者の利便性向上が可能です。特に外国人観光客が多い地域では、多言語対応のデジタルサイネージを活用することで、スムーズな案内が可能です。また自治体の公共施設では、防災情報や緊急時の避難案内を即座に表示できるため、安全対策としての導入が進んでいます。
デジタルサイネージの市場規模と今後の展望
デジタルサイネージ市場は近年急速に拡大しており、企業や自治体による導入が進んでいます。特にクラウド管理型のデジタルサイネージやインタラクティブ機能を備えた最新モデルの需要が高まっており、世界的に成長を続けています。
市場規模の拡大
デジタルサイネージ市場は近年急速に成長しており、日本国内においても近年数千億円規模まで拡大しています。[※1]
特にオフィスや商業施設、公共インフラでの導入が進み、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として活用が拡大しています。また新型コロナウイルスの影響により、非接触型の情報提供ツールとしての需要が増加しました。自治体や医療機関ではリアルタイムで情報を更新できるデジタル掲示板としての導入が進んでおり、今後もその活用範囲は広がると考えられます。さらに広告業界でもターゲットに応じた動的なコンテンツ配信が可能になることから、マーケティングの新たな手法として注目されています。
今後の技術革新と展望
デジタルサイネージの進化を支える要素として、AIや5G通信の活用が挙げられます。
AIを搭載したサイネージは、カメラやセンサーを用いて視聴者の属性を分析し、ターゲットに応じた広告を自動配信することが可能です。これにより効果的なマーケティング施策を展開できるようになります。また5Gの普及により、従来の静止画や簡単なアニメーションだけでなく、高解像度の動画をリアルタイムで配信できる環境が整ってきています。さらにタッチパネルや音声認識技術を活用したインタラクティブ機能の進化も進んでおり、オフィスの受付や商業施設の案内システムなど、双方向のコミュニケーションが可能なデジタルサイネージの活用が広がっています。
今後の課題と展望
デジタルサイネージの市場が拡大する一方で導入における課題も存在し、特に初期投資コストの高さや運用管理の負担が企業にとってのハードルとなることがあります。
クラウド型の管理システムが普及することで運用の効率化が図られていますが、通信インフラの整備やデータセキュリティ対策などが今後の課題です。また屋外設置においては、耐久性や環境要因への対応が求められ、継続的なメンテナンスが必要になります。
しかし技術の進化により低コスト化が進むことで、導入しやすい環境が整っていくと考えられ、今後はより柔軟で効率的な運用が可能なデジタルサイネージが登場してさまざまな業界での普及が一層進むことが期待されています。
2.どれを選ぶ?デジタルサイネージの種類と選び方
デジタルサイネージを導入する際、目的や設置環境に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。サイネージの種類によって運用方法や管理の手間、導入コストが異なるため、自社のニーズに合ったモデルを選定することが求められます。また設置場所や視認距離によっても適したスペックが変わるため、慎重な検討が必要です。
ここではデジタルサイネージの主な種類とそれぞれの特徴、さらに選定のポイントやコスト面の考慮事項について解説します。
デジタルサイネージの主な種類と特徴
デジタルサイネージには大きく分けてスタンドアロン型、クラウド型、インタラクティブ型の3種類があります。それぞれの特性を理解し、用途に合ったものを選ぶことが重要です。
スタンドアロン型
スタンドアロン型は、USBメモリやSDカードを利用してコンテンツを手動で更新するシンプルな方式です。
| 特徴 | インターネット接続を必要とせず、比較的低コストで導入可能。 |
| メリット | 初期投資が少なく、設置が簡単で小規模な環境に適している。 |
| デメリット | コンテンツの更新作業が手動のため、大規模運用には不向き。 |
クラウド型
クラウド型は、インターネットを経由して遠隔でコンテンツの更新・管理ができる方式です。
| 特徴 | クラウド上でコンテンツを一括管理し、複数のサイネージを一元的に制御可能。 |
| メリット | 全国の拠点や複数のディスプレイを統一したコンテンツで運用可能。 |
| デメリット | インターネット接続が必要で、月額利用料などのランニングコストが発生する。 |
インタラクティブ型
インタラクティブ型は、タッチパネルやセンサーを利用して、利用者と双方向のコミュニケーションが可能な方式です。
| 特徴 | タッチ操作や顔認識、QRコードスキャンなどの機能を備えた高機能モデル。 |
| メリット | 来訪者に合わせた情報提供ができ、店舗や観光案内所での利用に適している。 |
| デメリット | 高機能な分導入コストが高く、システム開発が必要な場合もある。 |
設置場所ごとの選び方のポイント
デジタルサイネージを導入する際には、設置場所に応じた適切なモデルを選ぶことが重要です。環境に合わない機種を選ぶと視認性が低下したり、耐久性の問題が生じたりする可能性があります。
屋内用と屋外用の違い
デジタルサイネージは設置場所の環境に大きく影響を受けるため、屋内用と屋外用の違い を理解して選定する必要があります。
屋内用
オフィスや商業施設、病院などで利用されることが多く、輝度(明るさ)は 300~500cd/㎡ で十分です。ディスプレイのデザイン性が重視されることが多く、インテリアとの調和を考えた設置が求められます。
駅やバスターミナル、イベント会場などで使用される場合、日光や天候の影響を受けるため、高輝度(1000cd/㎡以上)かつ防水・防塵性能(IP65以上)を備えたモデルが必須です。風雨や温度変化に耐えられる耐久性も考慮しなければなりません。
壁掛け型と自立型の選び方
設置スペースや使用用途によって、壁掛け型と自立型のどちらが適しているかを判断します。
壁掛け型
限られたスペースを有効活用できるため、オフィスの受付や商業施設の案内用として適しています。また企業のエントランスに設置することで、ブランドイメージを高める効果も期待できます。
自立型
スタンド式で移動が可能なため、イベント会場や展示会、店頭プロモーションなどに最適です。レイアウト変更が容易で、臨機応変な運用が可能になります。
視認距離に応じた適切な画面サイズ
デジタルサイネージは視認距離に応じた適切なディスプレイサイズを選ぶことで、最大限の効果を発揮します。
近距離(1~2m)
画面サイズは32~43インチ程度が最適です。受付やエレベーター前、会議室案内などで活用されます。
中距離(3~5m)
画面サイズは50~65インチが推奨されます。店舗のプロモーションやオフィスの共用スペースなどで活用が最適です。
遠距離(5m以上)
画面サイズは75インチ以上の大型ディスプレイが必要です。駅や空港の案内表示、屋外広告での活用に向いています。
選定時に考慮すべきスペックとコスト
デジタルサイネージを導入する際は、コスト面も重要なポイントとなります。単なる導入費用だけでなく運用コストやメンテナンス費用も考慮し、トータルコストを把握することが必要です。
解像度とディスプレイ性能
一般的なオフィスや店舗ではフルHD(1920×1080)が標準ですが、より高精細な映像を求める場合や企業のエントランス、大型商業施設向けでは4K(3840×2160)がおすすめです。特に大型ディスプレイを使用する場合や、近距離で細かい文字や画像を表示する用途では、高解像度のモデルが適しています。
輝度と視認性
屋内で使用する場合は300~500cd/㎡の輝度が適していますが、屋外では直射日光の影響を受けるため、1000cd/㎡以上の高輝度ディスプレイが必要です。また反射防止(ノングレア)加工が施されたディスプレイを選ぶことで、外光の影響を抑え、視認性を向上させることができます。
運用コストと管理のしやすさ
スタンドアロン型は導入費用が安い反面手動での更新が必要なため、運用負担が増加します。一方クラウド型は月額費用がかかるものの遠隔管理が可能で、運用の手間を削減できます。さらにインタラクティブ型の場合は、システム開発費用が発生するため、導入前に詳細な費用試算が必要です。
3.デジタルサイネージを導入するメリット
デジタルサイネージの導入には、情報発信の効率化やコスト削減、ブランドイメージの向上など、さまざまなメリットがあります。従来の紙媒体に比べてデジタルコンテンツを活用することで視認性が高まり、リアルタイムで情報を更新できるため、柔軟な運用が可能です。特にオフィス環境や商業施設では、業務の効率化やマーケティング戦略の強化にもつながります。
ここではデジタルサイネージを導入することで得られる主なメリットについて詳しく解説します。
デジタルコンテンツの活用で情報発信が変わる
デジタルサイネージを導入する最大のメリットは、情報発信の手段が多様化して視認性が向上することです。
動画やアニメーションによる訴求力の向上
紙媒体では静止画しか使えませんが、デジタルサイネージでは動画やアニメーションを活用することで、より目を引くコンテンツを配信できます。これによって通行人や訪問者の注意を引きやすくなり、情報の伝達効果が高まります。
リアルタイムでの情報更新が可能
デジタルサイネージは、ネットワーク経由でコンテンツを即座に更新できるため、最新の情報を常に発信することが可能です。例えばオフィスでは緊急の社内通知を即座に反映でき、商業施設ではタイムセールの告知をリアルタイムで表示できます。
時間帯やターゲットに応じたコンテンツ配信
クラウド型のデジタルサイネージを活用すれば、時間帯やターゲットに応じた広告や情報を自動で切り替えることができます。例えば朝は企業情報を表示し、昼は来訪者向けの案内、夜はプロモーション動画を流すなど、シーンに応じた運用が可能になります。
ランニングコスト削減と運用効率向上
デジタルサイネージは従来の広告手法や情報掲示に比べ、ランニングコストの削減と運用効率の向上にも貢献します。
印刷コストや設置作業の削減
紙のポスターや掲示物は定期的な印刷や貼り替え作業が必要ですが、デジタルサイネージであればコンテンツをデジタル化することで印刷費や人件費を削減できます。特に頻繁に情報を更新する企業では、大幅なコストカットにつながります。
遠隔管理による業務負担の軽減
クラウド型のデジタルサイネージであれば、遠隔地から複数のディスプレイを一括管理できるため、各拠点での作業負担が大幅に軽減されます。例えば全国に店舗を展開する企業では、本社からすべてのディスプレイを制御し、統一された情報を発信することが可能です。
自動化による運用の効率化
スケジュール設定機能を活用すれば、決められた時間にコンテンツを自動で切り替えることが可能です。例えばオフィスでは、始業前に社内ニュースを配信し、営業中は製品情報を表示、退勤時間にはリマインダーを流すなど、業務の流れに合わせた活用ができます。
企業ブランディングへの影響
デジタルサイネージは、企業のブランドイメージを向上させるツールとしても効果を発揮します。
視覚的なインパクトの強化
デジタルサイネージは、紙媒体では実現できない動画やアニメーションを用いた表現が可能です。これによって企業のメッセージやコンセプトをより鮮明に伝えることができます。特に受付や会議室前に設置することで、来訪者に対して企業の最新情報や取り組みを視覚的に訴求し、信頼感を高めることができます。
ブランドデザインの一貫性を強化
デジタルサイネージは、企業のロゴやブランドカラーを活かしたコンテンツを柔軟にデザインできるため、ブランドの統一感を保ちながら情報発信が可能です。例えば全社共通のテンプレートを作成し、全国の拠点で統一したデザインのコンテンツを配信することで、企業のブランドイメージを統一し、認知度を高めることができます。
SNSやWebコンテンツとの連携
近年ではデジタルサイネージをSNSやWebサイトと連携させ、リアルタイムで情報を更新するケースが増えています。例えば企業の公式TwitterやInstagramの投稿をサイネージ上に表示することで、ブランドの最新情報を顧客に届けることができます。これによってオンラインとオフラインの情報発信を統一し、顧客との接点を増やすことが可能になります。

4.おすすめのデジタルサイネージモデル3選
デジタルサイネージの導入を検討する際、どのようなモデルを選ぶかは重要です。設置環境や用途に応じて必要な機能やスペックが異なるため、自社のニーズに合った製品を選ぶことが求められます。
ここではクラウド型、高解像度ディスプレイ、屋外対応モデルという3つのカテゴリーに分けて、おすすめのデジタルサイネージモデルを紹介します。
使いやすいクラウド型: BrightSign LS423

出典:ジャパンマテリアル株式会社(https://jmgs.jp/products/brightsignls3series.html?utm)
おすすめポイント
・フルHD動画の再生対応
・多彩な機能の搭載
・コンパクトな設計
BrightSign LS423は、シンプルなデジタルサイネージ運用に最適なエントリーモデルです。
フルHD動画の再生に対応しており、H.265およびH.264形式の高品質な映像をスムーズに表示できます。さらにネットワーク配信機能を備え、遠隔地からのコンテンツ管理が可能です。
また同期再生やUSBデバイスとの接続にも対応し、複数のサイネージを連携させた運用にも適しています。コンパクトな設計によって限られたスペースでも設置しやすく、オフィスや店舗など幅広いシーンで活用できます。
コストを抑えつつ高性能なデジタルサイネージを導入したい企業にとって、BrightSign LS423は最適な選択肢となるでしょう。
大画面で高解像度: LG 55UH5F-H
引用:LG 55UH5F-H
おすすめポイント
・ULTRA HD解像度とIPSパネル
・ノングレアコーティングによる高い視認性
・スリムデザインと狭額縁設計
LG 55UH5F-Hは、4K UHD(3840×2160)の高解像度 により、鮮明でリアルな映像を表示できるデジタルサイネージディスプレイです。
IPSパネルを採用してどの角度からでも色の変化が少なく、広視野角での高い視認性を実現しています。
またノングレアコーティングにより明るい環境下でも反射を抑え、テキストや映像の視認性を向上。屋内のさまざまなシーンでストレスなく情報を伝えることができます。さらに、狭額縁(上・右・左9.9mm、下14.4mm)とスリムデザイン(奥行き39.9mm)を採用し、設置場所を選ばずに洗練された外観を提供します。
オフィスや商業施設、会議室などでの導入に最適なLG 55UH5F-Hは、視認性・デザイン性ともに優れたデジタルサイネージディスプレイです。
屋外対応で耐久性抜群: Panasonic TH-55WF1HJ

出典:Panasonic CONNCT(https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/wf1h#support)
おすすめポイント
・超高輝度による優れた視認性
・明るさ自動調整機能による省エネ運用
・24時間連続稼働と縦置き設置対応
Panasonic TH-55WF1HJは、2700 cd/m²の超高輝度を実現したデジタルサイネージ向けディスプレイです。
一般的な業務用ディスプレイに比べて圧倒的な明るさを誇り、直射日光の当たる場所でも鮮明な映像を表示できます。そのためショッピングモールや交通機関、公共施設など、人の往来が多い環境での使用に最適です。
また明るさ自動調整機能を搭載して周囲の照度に応じてバックライトを最適化することで、省エネと視認性のバランスを実現します。さらに、24時間連続稼働に対応しているため、長時間の運用が求められる場所でも安定したパフォーマンスを発揮します。
設置の柔軟性も高く、縦置き・横置きの両方に対応しているため、利用シーンに応じた最適なレイアウトが可能です。高輝度・省エネ・耐久性を兼ね備えたTH-55WF1HJは、屋内外問わず、長期間の安定運用を求める企業にとって理想的な選択肢となるでしょう。
5.まとめ
本記事ではデジタルサイネージの基本から用途別の選び方、導入メリット、さらにはおすすめの製品まで解説しました。
デジタルサイネージは、オフィスや商業施設、公共機関などで活用される情報発信ツールとして、近年注目を集めています。リアルタイム更新や動画・アニメーションの活用によって視認性と訴求力を高めることができるため、紙媒体に代わる効率的な広告・案内手段となっています。
導入時には設置場所や用途に適した種類を選ぶことが重要です。クラウド型は遠隔管理が可能で大規模運用に適しており、高解像度ディスプレイはブランディングやプロモーションに最適です。屋外用モデルは耐久性と高輝度が求められるため、環境に応じた選定が必要です。
デジタルサイネージを効果的に活用して企業の情報発信力を強化しながら、業務効率の向上とコスト削減を実現しましょう。